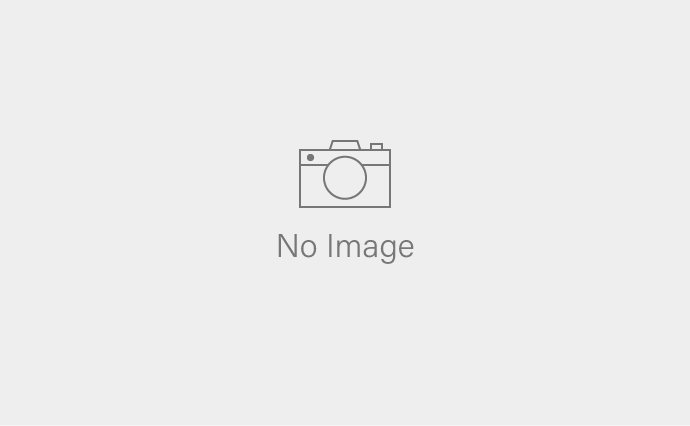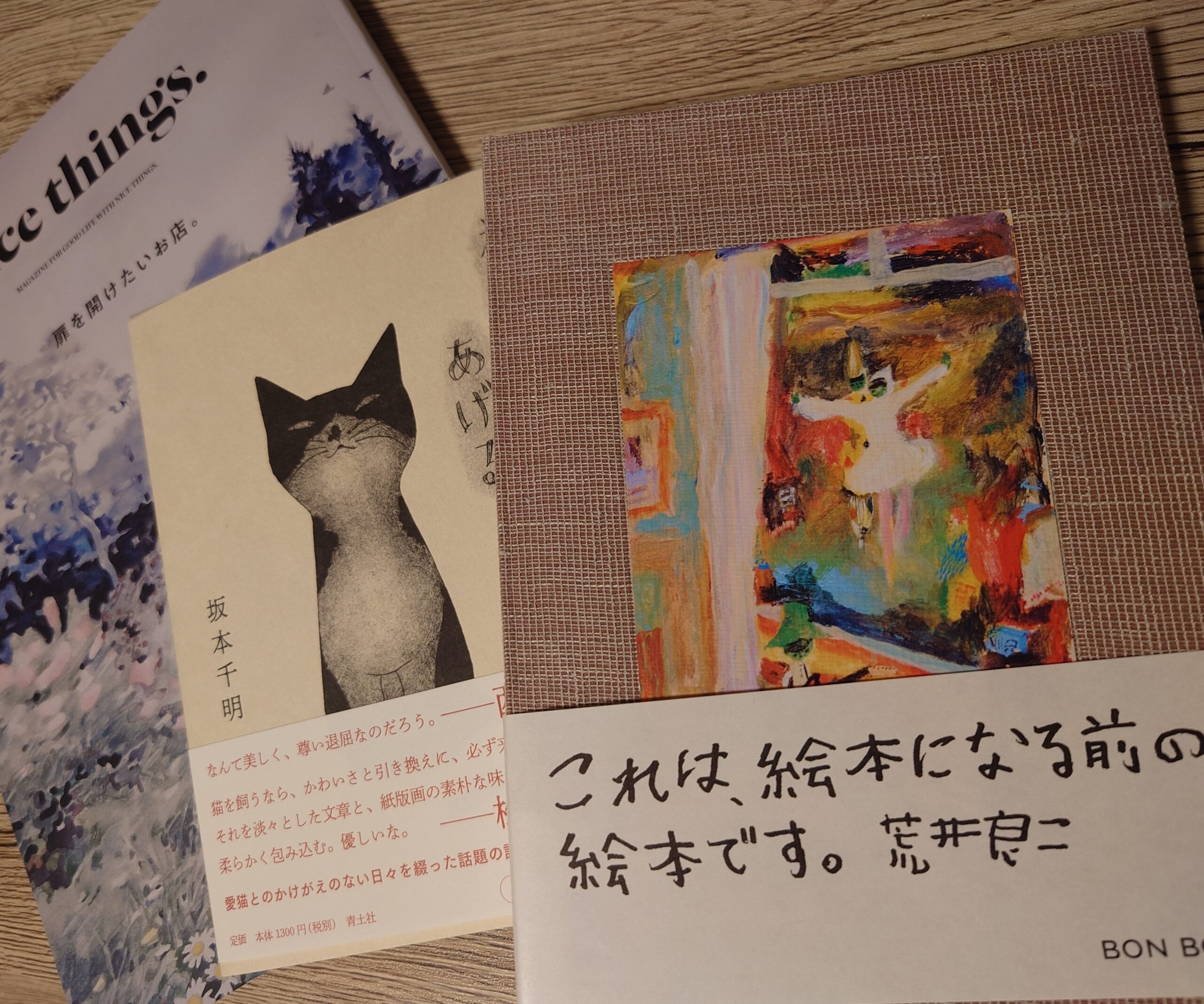― 技術と感覚のあいだで、心に寄り添う一杯を ―
はじめまして。MRoastCoffeeの真樹志(まきし)と申します。
福島市を拠点に、イベント出店や間借り営業を中心に活動している無店舗型の珈琲屋です。
初めての方は、こちらのページもぜひご覧ください。
なぜネルドリップなのか
出店の際、私はネルドリップで珈琲を淹れています。
最初の頃はペーパーフィルターを使っていましたが、今では特別な事情がない限り、ネル一択です。
理由は大きく三つあります。
- ネルドリップで淹れている人たちに憧れているから
- 技術によって味わいをコントロールしやすいから
- もっと多くの人にネルドリップの良さを知ってほしいから
憧れのネルドリップの人たち
ネルドリップは、ハンドドリップの中でも古参の技法。
私の地域でも、ネルで淹れているお店は少なくなってきました。
もかの標さん、大坊珈琲店の大坊さん。
どちらも書籍でしか知りませんが、珈琲への向き合い方に深く共感しています。
(大坊さんの珈琲、いつか飲めるうちに飲みたいな…)
福島市にも、ネルドリップで淹れる素敵なお店があります。
私が珈琲に惹かれるきっかけになった「じゃ豆(じゃず)」さん。
そして、そこまで遠くない場所にあった「SEKIYA COFFEE」さん。
どちらも、ネルドリップを選んだのは偶然でした。
でも今では、運命だったと思っています。
じゃ豆さんでは、焙煎の理論や時代背景、ネルの歴史まで、私の成長に合わせて教えてくれました。
SEKIYAさんでは、抽出の実践や焙煎機の貸し出しなど、技術面で多くの経験を積ませてもらいました。
私の珈琲屋像は、まさに彼らのような存在です。
味わいをコントロールできるからこそ
ネルドリップは、見た目からして職人の道具。
実際、技術によって味わいの幅が大きく変わります。
初心者には扱いづらいかもしれませんが、慣れてくるとその幅の広さが魅力になります。
今では、ペーパーフィルターの方が狙った味を出すのが難しく感じるほどです。
だからこそ、私は「おいしいものを届けたい」と思ったとき、ネルを選びます。
ネルドリップの良さを伝えたい
ペーパーフィルターが主流になった今、ネルドリップは「珍しい」と言われることが増えました。
「ネルなんですね」「初めて見ました」——そんな声を、両手では数えきれないほど聞いてきました。
でも私は、これまで多くの人がつないできたネルのバトンを、次につなぎたい。
ネルでしか出せない味わいがある。
だから、消えてほしくないと思っています。
あえて“コントロールしない”という選択
味わいをコントロールできるからこそ、私はそのコントロールを手放すこともあります。
抽出時にタイマーやスケールは基本使いません。
サーバーも、目盛りのないハリオを選んでいます。
注文をいただいてから提供するまで、私はその珈琲のことしか考えられません。
スケールを使えば便利ですが、私は最大限お客様に寄り添いたい。
そのために、あえて使わないのです。
誤解してほしくないのは、「私は」ということ。
スケールを使うことが悪いわけではありません。
これは、私自身の甘えをなくすための工夫です。
何も見ずに180cc、200ccを淹れ分けるのは難しい。
でも、その過程で生まれる味の揺らぎにこそ、私は「面白さ」を感じます。
一定のクオリティで出てくる、あたたかいけどどこか冷たいチェーン店の珈琲ではなく、
心まであたたまるような、そんな一杯を届けたい。
それが、私がネルドリップを選ぶ理由です。